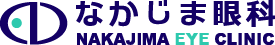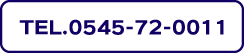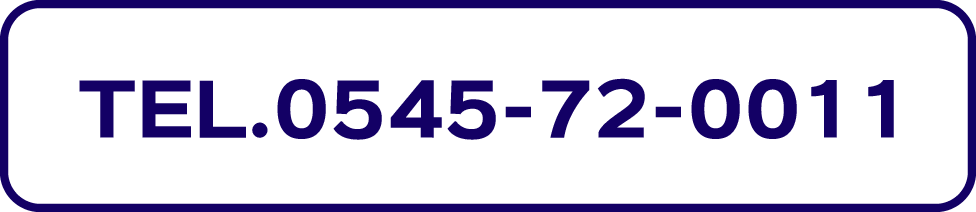手術・治療について
なかじま眼科は1988年の開院以来多くの手術経験のある、歴史と実績を持ったクリニックです。
- 1網膜硝子体手術に対応
- 黄斑前膜、黄斑円孔、硝子体黄斑牽引症候群、増殖性糖尿病網膜症、裂孔原性網膜剥離、眼内レンズ脱臼、破嚢症例などに対する網膜硝子体手術を行っております。
- 2難症例白内障手術に対応
- 難症例とされるZinn小帯脆弱・水晶体動揺・緑内障発作後・過熟白内障白内障にも対応。老眼矯正のできる多焦点眼内レンズの経験も豊富です。
- 3緑内障手術に対応
- 低侵襲緑内障手術、いわゆるMIGSに対応しております。目薬で眼圧のコントロールができなかったり、視野障害が進行している患者さんに対して、手術を施行しております。
麻酔について
なかじま眼科では治療における痛みに最大限配慮しています。白内障手術などの低侵襲手術は点眼麻酔のみでも施行可能ですが、複雑な操作を伴う手術を行う場合には、より長時間持続し、かつ深い麻酔効果を得ることが重要となります。現在行っている麻酔方法は以下の通りです。
- テノン嚢下麻酔
- 結膜(白目の表面)に切開を行い、そこから麻酔薬を注入する方法です。麻酔時のわずかな刺激感と、術後2週間程度の充血が生じます。ただし進行した緑内障であったり、過去に眼手術の既往があったりする場合には、結膜を温存する目的で敢えてこの麻酔方法を行わないことがあります。
- 経結膜的球後麻酔
- 結膜の表面から筒状のガイド針を挿入し、その中へ麻酔薬を注入する方法です。特に黄斑疾患に対する硝子体手術ではほぼ全例に行っています。下記に述べる経皮的球後麻酔と基本的に同等の麻酔効果ですが、ガイド針を用いるため眼球穿孔のリスクを軽減した方法です。
- 経皮的球後麻酔
- 裂孔原性網膜剥離や増殖性硝子体網膜症といった長時間の手術には主にこの方法を行います。また、黄斑疾患でも特に緊張しやすいかたには行う場合があります。上下のまぶたの皮膚から眼球の裏側の空間に向けて麻酔薬を入れるため、麻酔時の異物感や刺激感はやや強めですが、痛みと目の動きを強力にブロックできます。上記のような疾患を治療する際には大きな手助けとなります。術後1週間程度はまぶたが腫れた状態となりますが、時間とともに改善します。
- 伝達麻酔
- 眼瞼下垂などの外眼部手術の際には、眼窩上神経ブロックや滑車上神経ブロックなどの伝達麻酔を併用しています。神経の根本に麻酔薬を注入するため通常の方法よりも麻酔そのものによる痛みを軽減できます。麻酔効果が高く、麻酔薬の使用量も少なくて済むメリットがあります。術後1週間程度はまぶたが少し腫れた状態となりますが、時間とともに改善します。
- 点滴麻酔
- 点滴から鎮静・鎮痛効果のある薬剤を注入します。手術中に気持ちが落ち着いたり、浅い眠りについたりすることが可能です。ただし手術が終わった後も数時間効果が持続する場合があるため、直後から車の運転などをされる方には適さない方法です。また、いわゆる全身麻酔とは異なりますので、完全に意識が無い状態となるわけではありません。
各手術について
なかじま眼科での各手術については、下記より詳しくご説明しております。